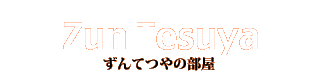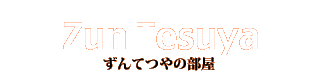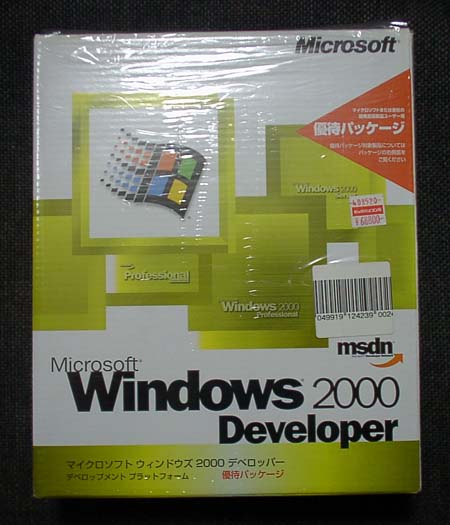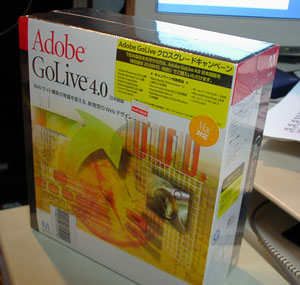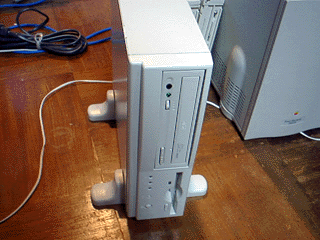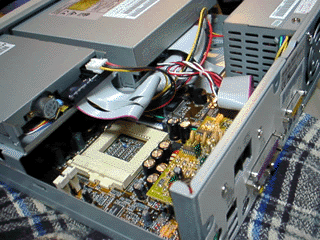<00-12-31>
今年一年のPCライフを振り返る
今年はやっぱりWindows2000の発売が一番大きな出来事だった。会社では、年頭に買った小型のベアボーンに2000を入れて使っているんだけど、これがすごく快適。安定しているし、使いやすいし、そこそこ速いし、Win98とかと比べるとぐっと良い。OfficeとPhotoshopとVISIOとか、重量級のアプリを同時に立ち上げても耐えてくれるし。会社でMacを使う事は減ったよなあ。
一方自宅の方は、いくつかの機器(Rioとか)の2000対応が遅れてたため、なかなか2000への完全移行が図れなかった。しかし、ようやく完全移行の準備がほぼ整った。
今でも自宅でのメインマシンはMacなのだけど、Webブラウザでの利用がほとんどで、実はMacならではの利点ってあまり出てない。来年のOS Xの出来しだいでは、自宅環境もMacから2000へ移行しかねないあたりが怖いなあ。また、最近はじめたビデオ編集に関しても、ツール類がWindowsの方が充実しているので、どうしてもWindowsにシフトしてしまう。まあ、時間を占有する作業はWindowsにやらせて、Macは空けておきたいと思いもあるんだけどね。うーん、Appleがんばってくれ。
<00-12-29>
プロスペック DVE773 \21,800@ビックカメラ
デジタルビデオ編集機。あるいはタイムベースコレクタ。って言うとなんだか分らないけど、俗に言うコピーガード除去装置。コピーガード除去装置の販売は禁止されたため、今は別名目の機械として売られている。カラーバースト信号と同期信号をそげかえてくれるので、マクロビジョンとかのコピーガード信号は除去される。プロスペックはコピーガード除去装置が一世を風靡した頃に評判だったメーカー。ここ以外にも数社から、今でも同種の製品は出ている。しかし、このプロスペックが一番派手に広告して、一般店頭にも置いている。そのうち摘発されるんじゃないかなあ…。って事で手に入るうちに買っておいた。これでDVDも安心してコピーできる。まあ、基本的にDVDをコピーする趣味はないんだけど、DV取り込みとかで遊ぶ際にDVDソースが使えるのは便利なので…。
<00-12-26>
MP3JUKEBOX 5 @ベクターオンライン \2,000
Becky! @ベクターオンライン \4,000
MP3JUKEBOXがバージョンアップ。CDライティング機能とか、使わない機能がほとんどだけど、Windows2000に正式対応したのがありがたい。オンラインアップグレードだと安いのも良い。ベッキーは、定番のメーラー。自宅はOutlook Express、会社はEUDORAを使ってたけど、気分一新で変更。メールの移行にちょこっと苦労したけど、最近は色々移行ツールが出てきてくれて助かる。ベッキーは使いやすいので、慣れると癖になる。
<00-12-16>
256MB SD-RAM \11,200@Q-bit
もういらないんだけど、メモリがどんどん下がるので買ってしまった。今回はちょっと割高だけど、256MBにした。128だと5000円以下で購入できる。NCPとかって言う、知らないメーカーのチップ。買った店はQ-bitと言う、旧O-bitの跡地に出店している怪しい店。でも、133-CL2でも動作したので、なかなか良好。そろそろパーツも余ってきたので、新しいPCが作れそうだなあ。
<00-12-09>
Matrox G450 \17,700@フェイス

二年ぶりにビデオカードを買い替える。ゲームをやらない俺には、3D機能の向上ばかりの昨今のビデオカードには興味がないのだが、ビデオ編集環境を手にしたので、NTSC出力も可能なデュアルヘッド機能に曵かれて、G450を購入。メモリはDDR仕様のものが32MB搭載されている。旧来のG200は8MBだったので大幅な増強。ただし、G450は前モデルのG400と性能的には大差ないらしい。大差ないというか、性能向上部分とコストダウンして省いた部分の相殺で+-ゼロと言ったところのようだ。
肝心のデュアルヘッド機能は最高!ソフトDVDプレーヤを起動すると、その映像出力がTVモニターに表示される。綺麗だ!TMPGEncでエンコードした映像を出力したら、すごく綺麗。ちなみに、ソフトDVDプレーヤでなくても、Media Playerなどで再生した画像も、映像部分だけがTVモニターで全画面表示される。満足度は高い。
一つだけ難を言えば、相変わらず1600×1200の解像度だと、ソフトDVDプレーヤが起動しない事。まあ、これはG450のせいと言うより、Win2000の標準DVDプレーヤが原因のような気がするが…(添付のJet Audio DVD Playerでも駄目)。ちなみに、一度低いレゾで再生して、プレーヤが起動している状態でハイレゾに切り替えると、1600×1200とかでも再生できるんだよなあ。なんかソフト的に制限かけてる感じだなあ。やっぱりWinDVDとか買わなきゃいかんかなあ…。
<00-12-09>
HP Jornada720 \94,800@ビックカメラ

JornadaがHPC2000になり生まれ変わった。CPUは旧来のSHからARMに変わり、クロックも大幅アップした。元々持っていた680はソフマップで売り払い、買い替える。680の売り値は720が発表されてからグングン落ちていったのだが、先般の液晶やらCFギミックの修理が幸いしてか、上限価格の25000円で売る事ができた。
新しいJornadaは色が少し渋くなったが外見上は大きな変化がない。しかし良く見るとCFギミックがなくなり、スマートカードリーダが新設されるなど、実際には内部設計は大きく変更されている。全般に、ハード的にやわな部分が改良されたみたいで、CFギミックの他、ボタン電池の挿入口もネジが撤廃され壊れにくくなっている。また、同期にUSBを使用できるようになったのも嬉しい改善だ。会社で使っているPCがレガシーフリーでシリアルポートがなく困っていたで、この改善は助かる。ただ、USBを用いた同期には、多少問題があるようで、うちでも突然同期が取れなくなり焦った。Jornadaをソフトリセットしたら直ったけど、原因は不明。
ソフトウェアとしては、Windows Media Playerが標準添付されMP3やWMAなどのオーディオファイルを再生できるようになったのと、Pocket IEがIE4相当になりかなりキビキビと動くようになったのが目新しい。Media Playerに関しては、ステレオヘッドホン端子も付いているため、Jornada自体をポータブルMP3プレーヤとして利用できるのが嬉しい。バッテリの持ちもいいし、他のアプリを動かしていてもMP3を再生できるので、新幹線の中などで重宝しそうだ。HP製のバックアップやダイアルアップなど各アプリケーションもバージョンアップされ、OminisolveなどのHPらしい新ソフトも追加されている。トラナビがARMに非対応でバンドルが見送られたのが残念だが、将来的に配付される可能性もあるようだ。
特に目新しさはないJornada720だが、生活の一部と化していただけに、スピードが速くなり、爽快な操作感が得られるようになったと言うのは、非常に満足度が高い。Jorandaは、概観に関しては680で完成された感があるので、今回のような内部的な改善にとどめると言うのが最善の選択と言えるだろう。もちろん、将来的なには、さらなる高集積化が進み、200LXのボディにCDが入るというのが一番好ましいのだが…。
<00-12-02>
NOVAC DVD再生エンジン \1,980@ヨドバシカメラ
Aplix WinCDR 6 upgrade \5,480@ヨドバシカメラ
ミツミ製FDドライブ \1,680@あきばお〜
NOVACのDVD再生エンジンは、待望の製品。NEC製のWIndows用ソフトMPEG2デコードエンジンをパッケージ化したもの。これをインストールすると、Windows 98/Me/2000に搭載されているMS製標準DVDプレーヤや、Windows Media Playerで、DVD-VideoやMPEG2ファイルが再生できるようになる。価格対満足度の高い商品で、これでMPEG2の扱いが楽になった! 再生映像の質も高く素晴らしいのだが、唯一の難を言えば、ソフトDVDプレーヤが結構環境を選ぶ事。また、今のうちのビデオカードだと、レゾを落とさないと再生できない。やっぱりビデオカード買い替えなきゃなあ。
次に買ったのがAplixのWinCDRの最新版。WinCDRは、軽快なのと相性問題が少ないのが良い。また、ここしばらく進めているアナログレコードのCD化の作業に、このソフトの波形モニタ&エディタの機能がすごく役立っていて手放せない。今バージョンの個人的な最大のお気に入りは、SONIC DVDit LEのバンドル。これで、DVDもどきが簡単に作れる。DVDもどきとは、CD-Rなんだけど、論理フォーマットはDVD-Videoという変則的なディスクで、さすがに民生用DVDプレーヤではかからないが、パソコンのソフトDVDプレーヤ環境なら問題なく動作する。CD-ROMドライブでももちろん問題ない。収録時間が20分程度と短いが、画質はVideoCDとは比べ物にならない。MPEG2ファイルの作成は、本ソフトとは無関係だが、フリーウェアのTMPEGENCを使用。TMPEGENCは、MPEGのライセンスの関係で、MPEG2エンコード機能が封印されてしまったが、一つ前のバージョンまではMPEG2ファイルもばりばりエンコードできる。2パスVBRとか高度な変換も可能。DVDitでビルド中にエラーが出たが、エラーメッセージを参考にして、TMPEGENCの設定をいじったら(シーケンスヘッダがデフォルトで0だったのを1に変えた)、うまくいくようになった。出来上がったDVD もどきは、インデックスメニューまで付いて、なかなか本格的。これでDVD-Rとか安くなったら最高だなあ…。
最後に購入したのが何とFDドライブ。ちょい前に98エミュレータに凝って、そのエミュレーション精度の高さに感動して、ATに本格的な98エミュレーション環境を構築するために購入。このドライブは3モードに対応しており、以前買ったFloppyMagicを併用することにより98の1.2MB FDも読めるようになる。98エミュレータは4種類くらいあるんだけど、一番のお気に入りはT98。98の実機のROMを吸い上げるので、エミュレーション精度も高いし、FM音源まで再現してくれるのが感動してしまう。これで、98環境は当面安泰だ。
<00-11-30>
Adobe GoLive 5.0 \9,380@ビックカメラ
結構GoLiveを使うようになったので、アップグレード。これくらい使ってるソフトだと、アップグレード料金も苦にならない。会社のイントラページの作成にも使ったのだが、Macを起動するのは面倒なので、Windows版も欲しくなってきてしまった。
<00-10-28>
OS Xをインストール
Mac OS X パブリックベータ \3,500@Appleオンライン
OS Xのパブリックベータが届く。HDDを増設しようかとも思ったが、当面あまり使いそうもないなあ、と思えたので、既存のHDDを整理してパーテーションを確保した。印象は…。うーん、ちょっと重いかなあ。アニメとかしすぎ。GUIもちょっとゴテゴテしすぎかも。前にBe OSをはじめて触った時には、その軽い動作にびっくりしたが、OS Xは重いなあ。Classic環境はさらに重い。こりゃ、CPUの動作クロックが倍くらいにならないと、実用的とは言えないぞ。しかし、半年後には、この環境に乗り換えなきゃいけないのか。うーん。
Windows 2000なんかは、98やNTのほとんどのソフトが動作したので、移行もさほど苦ではなかったけど、OS Xは結構厳しいかもなあ。リリースまでに主要ソフトが揃ってればいいけど…。
<00-10-25>
値段が下がりまくったメモリーを購入
PC100 SD-RAM 128MB \7,500*2枚@PC夢工房
なんかここ一ヶ月メモリの値段が下がり続けた。一万円切ったら買おうと思ってたけど、さらにどんどん下がり続けた。先が見えないけど、そろそろ下げ止まりじゃないかと言う噂があり、かつ給料も出たので買っておく。安モノのメモリーってノーブランドのケースが多いみたいだけど、今回のは、一応ブランドモノ(M-Tec)だった。まあ、M-Tecってマイナーメーカーだけど。
128Mビットチップ使っており、片面実装のメモリ。133のCL2でも動作するので、上出来だろう。とりあえずメインのPC/ATにさしたけど、ATに384MBもメモリー要らないなあ。ちなみに、メモリが下がる中、HDDの値段が上がるらしい。なんでも主要半導体の供給が滞っているとか…。上がると聞くと、買っておこうかとか、すぐ思っちゃうんだよなあ。いかんなあ。
<00-10-25>
修理完了
Jornadaはその後、完全にスタイラスが反応しなくなり、修理に出す。結局またディスプレイユニットとか全部交換。同一症状のなので無償にしてくれたけど、また再発するかもなあ。そろそろ買い替えを検討した方が良いのか?
Rioの方は新品交換。Rio500は日本では修理と言うのはやってないらしく、故障したら有無を言わさず交換みたい。まあ、無償だからいいけど。だから、故障原因などにも一切触れられていなかった。とにもかくにも、全部直って良かった。
<00-10-15>
いろいろ壊れる。
10年以上使ってきたソニーのディスプレイモニタ、KX-34HV2がある日突然映らなくなったのが9月終わり頃。修理に来てもらい、直るまで結局3週間もかかってしまった。はじめはブラウン管がいっちゃったかもしれないと言われて焦ったが、大事にはいたらなかった。しかし、TVのない生活は辛かった。TVなんて大して見ていないと思ってたんだけど、想像以上に依存度が高かったみたい。どうしようもなくてプロジェクタやパソコンキャプチャでTVを見たりもしたが、どうもしっくりこない。やっぱりTV重要だな。しかし、このKX-34HV2、重量が84kgもあるため、処分する事が難しいのが悩みの種。今回は直ったからいいけど、ブラウン管がいっちゃったら、本当にどうしよう…。サービスマンに聞いたら、ばらしても、ブラウン管部は3人掛かりで持たないと厳しいとまで言われちゃうし。うーん、デジタル対応TVが買えるのはいつに日になるやら…。
で、いろいろ壊れたいろいろは、他にRio500。電源が入らない。Jornadaも、3ヶ月前の現象が再発。でも、これはコールドリセットかけたら直ってしまった。うーん、ものが壊れるとへこむから嫌だなあ。もうほぼ修理する気ないけど、壊れたまま放置してあるのって他にも、AVアンプとかHi8デッキとかDATとかMDとかある。その多くはソニー製品だなあ。
<00-10-03>
音楽用CDレコーダ
パイオニアPDR-D5\39,800@ヨドバシカメラ

アナログソースサルベージ計画の一環で、アナログレコードのCD化を計画していた。当初は、SB Live!のオプチカルインを利用して、MDデッキをリアルタイムA/Dコンバータにして取り込もうとしたんだけど、SB Live!のデジタル入力にひどいノイズがのる事が判明。どうも、サンプリングレートコンバータとかの付加回路を、スルーでもなんでも必ず通るみたいで、著しく音質が劣化するようだ。efuさんのページとか見ると、波形が全然変わってる事が良く判る。
で、USB型の音声入力デバイス買おうかとか、結構悩んだんだけど、音楽用CDレコーダを買うのが一番無難ということで、落ち着いた。無駄な投資するくらいなら、ちょっとくらい高くついても確実な道を選んだ方が良いだろう。
購入候補には、一般のディスクも使えるタスカムの業務用機種とか、デジタルリミッターがついてるソニーの機種とかが上がってたんだけど、ヨドバシに買いに行ったら、パイオニアの機種がモデルチェンジ前で叩き売られていた。ポイント使うと3万円少々で買えるので、この機種に決定。使い方としては、一旦このレコーダで、アナログレコードの内容を通しでRWメディアに録ってしまって、PCでトラック分けする。で、最終的にはPCのCDRドライブでRメディアに焼き込む。このやり方だと、高価な音楽専用メディアは、RWを一枚買うだけで使いまわせるし、厳密なトラック分けも、PC上で波形を見ながら行える。
しかし、アナログプレーヤ発掘するのが面倒そうだなあ…。
<00-09-23>
ハードディスクとWindows Me
Maxtor M94098U6(40GB) \15,700@フェイス
カノープスのノンリニア編集をはじめたら、ハードディスクの容量が足りなくなったのと、気が付いたらMSDNでWindows MeのCDが送られてきていたので、これらを入れるために新しいHDDを買う。正確に言うと、これまでテンポラリに使っていた16GBをWindows Meに割り当て、新規に購入した40GBを、テンポラリに使うことにした。
し、しかし、Windows Me使い物にならんぜ! なんだこりゃ?
ビデオカードやサウンドカードをまともに認識しない。Matrox G200とかSB Liveだぜ。Win2000や98SEでは問題なかったのに、Meだと全然だめた。まあ、後からドライバ入れると動くようになるんだけど、Meだって当然こいつらのドライバ持ってるはずだよなあ? なんで認識せんのだあ?
しかも、ちょこっと使ったら、何か突然動きが遅くなったりして…。理由はさっぱり判らないんだけど、ネットワークドライブ開いてごそごそやってたら、突然レスポンンスが悪くなってしまった。再起動しないと直らないし。大丈夫か? Me。
それはそうと、一応、売りの機能である自動復旧機能は試してみた。確かにちゃんと、インストール直後とかに戻してくれるけど、この機能探すのが大変だった。ヘルプか何か開くと頭にこの機能あるんだけど、普通はコンパネとかに用意するよなあ。判りづらいよ。MovieMakerとかもひっそりと眠ってるし。いずれにしても、どうも好きになれんな。このMe。98SEの方がマシだよ。まじで。
<00-09-08>
ノンリニア編集環境を整える
カノープスDVRaptor New Edition 58,800円@ヨドバシカメラ
ソニ−メディアコンバータ DVMC-DA2 28,000円@ヨドバシカメラ

仕事でちょろっとカノープスのノンリニア編集システムをいじったら、すごく操作性が良くてびっくりしてしまい、ついつい購入。DVベースのノンリニア編集なんて重くて、高嶺の花で、なんて思ってたけど実際使ってみたら、そんな印象は払拭された。
DV機器は持ってないので、ソニーのメディアコンバータも一緒に購入。これは、通常のアナログビデオ信号をDVに変換するハードウェアコーデックBOXだ。双方変換可能で、ダビングなんかにも使える優れもの。これで何をするかと言うと、古くなってデッキのメンテも不安になってきたベータのテープのサルベージだ。まあ、手間かかるんで本当にやるかどうか判らないけど…。
このシステムで、DVの状態で編集して、MPEG1に変換、最終的にはVideoCDに仕上げようという事。しかし、使ってみて一つ問題発覚。カノープスのアナログオプションキットで提供している、MPEG1変換機能が、Windows2000では動作しないのだ。残念だが、Windows98環境で使う事にする。操作性は良好で、キャプチャも編集もさくさくできる。DVは、10分弱で2GB以上のHDDを浪費するので、数年前は実用的ではなかったが、今は80GBのHDDとかが3万そこそこの値段なので、全く問題ない。CPUも速くなり、ソフトプレビューとかも全く問題なしだ。フレーム単位の編集も簡単にできるので、本当に使いやすい。快適。取り込んだDVファイルは、インデックスポイント毎にばらばらに分解し、それぞれをMPEG1で書き出す。しかし、HDDに熱がこもってるのか、この変換の時に何度か固まってしまった。原因不明。
完成したMPEGファイルを、Easy-CDのVideo CDクリエイタ機能でVideoCDに仕上げる。完成したVideoCDをDVDプレーヤにかけると、見事にTVモニターで再生された!
CD-Rとのつきあいは長いのだが、実はVideoCDを作ったのは初めてで、結構感動してしまった。言われていた通り、パソコン上で再生するより、TVモニターに映し出す方が綺麗に見える。一つ難点を上げると、ファイルを細かく分けたのだが(音楽ものだったので、曲ごとに分けた)、ファイルの換わり目で一瞬映像がフリーズするのだ。しかし、まあ、全体に出来は思った以上に良い。BS放送をS-VHSで録画したものがマスターだったのだが、市販のビデオソフトを買ってきた気分に浸れる。
<00-08-16>
DV7000であらためてDVD視聴
ずっと眠ってたDV7000をようやくセットアップ。視聴してみる。
あっさりした画像で、画像補正とかがあまり掛けられてない感じで好感が持てる。パイオニアのDVL-919と比較すると、919が眠たい感じで、7000がしゃっきりしている。ただ、MPEG固有のブロックノイズや、ジャギーが目立つ。制作者クレジットなどのテロップは特に目立つ。これまではあまり気になった事はなかったんだが…。これらは、TVモニターだとあまり判らないけど、プロジェクタで見ると、ハッキリ判る。それから、話には聞いていた、リモコンの使用感は、確かに悪い。上位機種のDV18はもっと酷いそうだが、一体どんな感じなんだろうか? レイアウトが悪いし、早送りとかも、ボタンを押すたびにスピードが変わるのだけど、うまくコントロールできない。
リージョン1ディスクの再生は、何ら問題なしで、MATRIXの輸入盤で再生確認を行った。
<00-08-14>
ビクターJX-S777 60000円くらい。忘れた。

6月に買ったのだが、DVDプレーヤ同様、場所を確保できず箱のまま放置していた。一念発起して、AVラックを整理。古いセレクタやBSチューナを捨て、場所を確保する。セレクタは、元々、ソニーとビクターのを一台ずつ持っていて、13入力に対応していた。しかし、1年ほど前に、揃って壊れてしまい、困り果てていた。特にソニーのは、マトリックス型のセレクタで、ものすごく使いやすかったので気に入っていただけに残念。しかし、後継機も出る気配がない。ここ一年は、TVチューナの4入力のセレクタ機能を使っていたが、さすがにCATVチューナとかも加わり、厳しい状態が続いたので、ビクターの最新機種を購入。
結構出来は良くって、フロントも入れると8入力あり、1394も3系統備わっている。まあ、1394機器なんて持ってないんだけど…。マトリックス機能はないが、二系統ダビングに、独立したダビングモニタも可能。これでようやく、手持ちのAV機器は全て接続可能になった。
<00-08-11>
Retrospect Express 4.3J upgrade 2000円
バックアップソフトのRetroaspect exがマイナーバージョンアップ。Mac OS9への対応と、ハードディスクへのバックアップが可能になったのが主な変更点か。ハードディスクへの対応は結構大きい。これで、フルバージョンのRetrospectとの差異は少なくなった。
製品とは関係ないのだが、今回、Software Too.にバージョンアップを頼んだのだが、対応がまずく少々腹たってしまった。クレジットカードにまつわるものだったのだけど、こっちの書類は正しいのに、きちんと見てないんだよなあ。しかも、向こうからのメールには「。。。」とかって、友達メールみたいな表記あるし。大丈夫か?
<00-07-28>
Adobe Illustrator 9 \24,800 @ヨドバシカメラ
ついに待望のオブジェクトの透明化機能が実装されたIllustrator。FreeHandに遅れること、2年か、3年か?
使おうと思ったが、なんか突然フリーズしたりして使用を断念。ちょっと切羽詰まった作業してたんで、原因を特定する余力がなかった。こんど、きちんと使ってみよう。
<00-07-01>
半期に一度のデータバックアップ
半年に一度、MacとWindowsとサーバのHDDをCD-Rにバックアップしている。今回はついに10枚になったしまった。DDSのテープでもいいんだけど、長期保管と言う意味では今一つ不安なので、CD-Rにしているのだが、コストパフォーマンスも一番良い。今回のメディアはビクターのを使ったけど、一枚70円台だもんね。でも、さすがにディスクの入れ替えは面倒。実はそろそろ、4.7GBの新しいDVD-RAMとか良いのかもしれない。
それはそうと、CD-Rにバックアップしていて、サーバ上にいくつか死んでいるファイルを見つけてしまった。CHKDSKかけたら、削除されたけど、何の拍子におかしくなったのやら。でも、NTBACKUPではエラーもなくバックアップされたてたから不思議だなあ。やっぱり、半年に一度の総バックアップは必須かもしれない。
それから、なんか久々にCD-R使ったら、Toast4はまともに動かないし、Windowsの方はブルースクリーンに落ちるし…、なんかメタメタ。まいった。
<00-06-30>
Maxtor DiamondMax60 60GB 27,500円@コムサテライト2
サーバのHDDがそろそろひっ迫気味なので、HDDを入れ替え。これまで4+16+16だったのを、4+16+60で合計80GBに。それにしても、HDDは安くなったもんだ。MaxtorのDiamondMax60は、5400RPMだけど、15GBプラッタで、バッファも2MBあり性能もなかなか良い。サーバにはちょっと勿体ないくらいなんだけど、コストパフォーマンスが一番良いHDDもこれだったりするんで、こうなってしまった。
<00-06-29>
Norton AntiVirus Premium 2,980円@ファミリーマート
今日からデジキューブ扱いでコンビニでノートンアンチウィルスが販売されるというので、買ってみた。本当にパッケージがコンビニにおいてあるのか疑問だったんだけど、ゲームとかと一緒にカウンターの棚に並んでた。店員はこれが何なのか良く判ってないようだったけど。このコンビニ版のアンチウィルスって、90日間のウィルス定義ファイルのダウンロードしかできないんだけど、Mac、Windowsハイブリッドで、両方使える。延長したければ、+1500円払えば、一年分の定義ファイルのダウンロードが可能になる。(ただし、これはMac、Winのどちらか一方のみ)
結構安いし、コンビニでこういう定番ソフトが買えるのって良いよね。Norton Utilityとかもコンビニに置いてあると、いざと言う時役に立ちそう。
<00-06-22>
話題のリージョンフリーDVDプレーヤを購入
マランツDV7000@ヨドバシカメラ \59,800

簡単にリージョン変更できることで話題のマランツのDVDプレーヤを購入。巷では確信犯と言われている。これまでもファクトリセッティングモードに入れるDVDプレーヤはあったが、これほどまでに簡単に変更できるのは、前例がないらしい。DV7000にするか、上位機種のDV18にするか悩んだけど、設計そのものはほとんど同じなのと、どちらの機種にしてもプログレシブもD端子も備わってないので、あまり高いのを買っても意味がないだろうと言う事で、下位機種の方にした。もう一つ下にDV4000というのもあり、これもリージョン変更できるんだけど、こっちはアカイのOEMで、リージョン変更のやり方が面倒だし、性能もぐっと落ちる感じなのでパスした。
セッティングは後日に見送る事にして、取りあえずリージョン変更を確認したが、問題なく変える事ができた。もしかしてファームを変更しているのでは…という不安もあったのだが、何ら問題はなかった。リージョン0(フリー)に加えて、1〜8まで簡単に設定できる。忘れないようにここに方法を書いておこう。
リージョン1〜8
・NO DISC表示の状態で、次曲と前曲ボタンを同時に押す。
・現在のリージョンコードがディスプレイされる。
・その後早送りボタンで希望のリージョンに合わせ、プレイボタンで確定。
・プレイボタンを押さずに電源を切れば変更されずに元に戻る。
リージョン0
・NO DISC表示の状態で、次曲と前曲ボタンを同時に押す。
・現在のリージョンコードがディスプレイされる。
・5秒間ストップボタンを押して、リージョン0とディスプレーされたらプレイボタンを押して確定。
これで輸入DVDも簡単に再生できるぜ!
<00-06-21>
Jornada680リペアセンターより帰還
一ヶ月くらい前から、Jornadaのスタイラス調整がすぐ狂ってしまうという問題が頻繁に発生するようになった。HPのCSに電話すると、フルリセットしてそれでもダメなら修理に出してくれと、と言われたが、フルリセット直後の状態でしばらく使うって、なかなか出来ないので、ハード的な問題なのかソフト的な問題なのか切り分けられずにいた。そうこうしているうちに、保証期間切れそうなので、無視して修理に出す事にした。まあ、俺のJornadaは水没実績のあるものなので、ばれれば無償修理の枠から外される事は間違いないんだけど、駄目もとでチャレンジ。ついでなんで、最近気になってた、CFスロットの浮きと、CFメモリのエラー表示についても修理依頼表に記載して、宅急便でHPのリペアセンターに送ってしまった。
一週間もすると、HPからJornadaが返送された。修理伝票を見ると、な、なんと7つもの部品を交換している。Display Assyとか、ACCDN Assyなんてのも交換されている。実際、実機を触ってみると、カバーの開閉部は新品のように固くなり、CF挿入部もすっかり直っている。ごっそり部品変えてくれたみたいだ。ラッキー。こりゃあ、まともに修理してたら、ウン万はしてるぞ。
でも、どうもまともに症状の確認もせずに、関連しそうな部品をごっそり変えたんじゃないかなあ? しかし、まあ、とにかくラッキーだ。
<00-05-27>
Planex5ポートリピータハブ 1940円@俺コンハウス
屋内のLAN配線を変更するために、10Baseのリピータハブを一つ買う。安いよなあ。コンパクトでマグネット付きなので、スチール板に簡単に取り付けることができる。
<00-05-12>
MSDNの初回送付分届く

Win2000devの、MSDN登録をしたので、4月分のCD-ROMライブラリ−が送られてくる。すごい量。巨大なバインダ−3冊分で、CD-ROMは100枚くらい入ってた。各国語版のWindows95、NT Workstation、Server、Enterprise、Terminal Serverが入っている。Winodows98と2000(Pro/Server/Advanced Server)に関しては、英語版と日本語版だけだが、ちゃんとホログラム印刷のCDだった。しかし、すごい量だなあ。中国、韓国、タイとか色々入ってるけど、使い道あるのだろうか?
<00-05-09>
MS Office 2000 Premium UPG \26,000 @ MS直販
MCP特別通販の最終日に申し込み。結構安かったし、Officeは使うのでちゃんと買おうと思い立ち発注。しかし、国内のSR-1のリリースはいつなのかな?
<00-05-08>
CATVついに開通!
本日以降、CATV関連の内容は、新設の常時接続の日々に書いていきます。
<00-05-06>
LINKSYS Cable/DSLルータ BEFSR41 $169@outpost.com

CATV加入を直前に控え、outpostで発注していたケーブルルータが航空便で届く。送料込みで188ドルの安さだ。プラスチックの筐体で、オモチャっぽいけど、デザインは悪くないし、機能も必要十分な感じだ。スイッチングハブの機能も合体しており、4ポートのLAN用の10/100Base-Tコネクタが付いている。IPマスカレレードや、ポートフォワード、DNS伝達などの各機能も搭載されている。プアーだが、IPフィルタリングの設定も可能だ。ルータ用にLINUXを組むのも仰々しくて面倒なので、この程度の製品で十分だ。LINKSYSってのは、日本で言うところの、PLANEXのような存在で、家庭用LAN製品のプライスリーダー的存在で、値段だけでなく、デザインや機能面でも、他社がやらない新しいものを入れたりしてくる。他にも、簡易ファイルサーバ兼プリントサーバのネットワークアアプライアンスや、電話回線を利用したHomePNAなどをリリースしている。
九十九電機下北沢店
近く(と言っても電車にのらなきゃなんないけど)に九十九電機が出来たので行ってみる。駅のすぐそばなのに加えて、店内も奇麗で、フロア数も多い。自作系のパーツフロアもあって、秋葉原と変わらないプライスと、気の利いた品ぞろえで充実している。秋葉原では意外と入手しづらいアルファのファンなんて全てあるし、バルクのビデオカードとかもほとんどの種類がおいてあった。書籍フロアや周辺機器も必要十分で、ちょっとした買い物なら秋葉原に行く必要もないだろう。これで、もっと近くにありゃあなあ。
<00-04-26>
CATVの現場下見
CATV業者が、工事の下見にやって来た。うちの前の電柱まで、ケーブルはきているそうで、直接壁に引き込めるようだ。
引き込み用の穴も、既にTVや電話線引き込み用のがあり、それをそのまま使える。しかし、それでも契約料と工事費で60000円もかかる。結構高いな。
工事は意外と早く、連休明けすぐにできるとのこと。月々の料金は、TVとメールアドレスの付加も入れて、税込み8400円。料金的には微妙な感じ。スピードが維持できれば問題ないんだけどね。ちなみに、現在加入者は800人で、月に200人くらいのペースで増えてるらしい。つい先日、完全に落ちた事があったようなので、サービスの質も少々気になるところだ。でも、もうゴーをかけちゃったんで、連休明けには常時接続環境だ。ルーター発注しなきゃ。
<00-04-18>
CATVついに申し込み
NTTのISDN常時接続サービスが受付開始。悩んだあげく、CATVの方に入ることにした。電話してみると、6月に上流6Mに拡張すると言うし、ルーターの使用に関しても、未サポートそいう条件で黙認してくれるみたいだし、言うことなし。ちなみに、現状世田谷エリアに関してはスカスカ状態らしい。
ただ、工事に関しては、基本1ヶ月待ちで、近くの電柱までケーブルが来ていない場合は、引き込み(東電やNTTの電柱借りるらしいが、申請に時間かかるらしい)に1〜2ヶ月追加で要するとのこと。現場検証には2週間くらいできてくれるらしい。
最近TV見ないのだが、ついでなのでテレビ放送の方も申し込んでしまった。しめて月7800円。ISDNの通信やめて、今契約しているISPを2社から1社に減らせば、トントンくらいに収まりそう。
さあ、これでルーター買わなきゃ。物欲に火がつく。どれにしようか?
<00-04-17>
MP3 JUKEBOX 4.4J
知らないうちにバージョンアップしていた。しかもエンコードエンジンが、XingからIISに変更になってる。IISはMP3の本家だし、音の評判も高い。MP3 Jukeboxの唯一の泣き所が、これで解消された訳だ。
でも、なぜかバージョンアップの案内のメールがきてない。よくよく調べると、ユーザー登録してなかったみたい。ベクターオンラインでアップグレードしたので、自動的に登録されるのかと、甘い事考えてたんだけど、あらためて登録の必要があったようだ。で、オンラインで登録すると、翌日にはバージョンアップの案内のメールが届く。なんと、タダ!
エンコードエンジンの変更という、大きな変更(少なくともライセンス料はかなり払ってるよな)にもかかわらず、タダとは、なんと大盤振る舞い!
で、使ってみたけど、スピードも速いし(これはCPU変えたからかも)、前より安定してるみたいだし、いいな。これで、メインのMP3エンコードを、Windowsに任せられる。
<00-04-16>
常時接続環境について考える
最近、真剣に常時接続環境への移行を考えている。もともと、昨年末のNTTのISDN常時IP接続の試験サービスに加入するつもりだったのだが、設備の関係でNGを出されてしまい、半年が経過してしまった。当のNTTのサービスは、半額に下げて今月半ばに受付を開始すると発表があったので、そろそろだろう。ISPの方も、俺が普段使ってるATTは通常の料金で対応するようなので万全だ。
しかし、最近ADSLやCATVでの常時接続環境の記事を見ているうちに、ISDNでは不十分に思えて来た。圧倒的に良さそうなのは、ADSL、特にNTT-MEのサービスなのだが、これは固定のグローバルIPを一つくれるらしい。現在のところ、下り512Kというのは守られているらしい。しかし、ADSLは俺の居る世田谷では利用できない。年末までは増強の予定もないらしいので、しばらく我慢しなければならない。しかも、ADSLは距離の問題やISDNとの干渉等、技術的な問題も多いと聞く。
一方のCATVは、ようやく今年に入って俺の済むエリアのCATV業者がインターネットサービスを開始した。CATVというと、東急の、馬鹿っ速いがテレホタイムには急激に遅くなる、などの話しが印象深く、あまり良いイメージはない。しかし、よくよく調べるとまんざらでもないようで、うちのエリアの業者は、コンスタントに200Kは出せているようだ。ピーク時は東急やADSLには及ばないが、まずまずの値だ。ただ、上流との回線が3Mであるとか、まだ不馴れのようで回線障害があった等、少々不安な面もかくせない。
そんなこんなで、最近妙に興味が湧いてきたのは、家庭用、SOHO用のファイアウォールとかルータ。LINUXで組むのも手ごろなんだけど、専用のアプライアンスが結構出ている。しかも、3万くらいのも出始めた。新しい機器への興味は尽きない。すっかり各社製品のスペックを調べて比較し尽くしてしまった。今のところマイナーなメーカーの製品しかないけど、半年もしないうちに、メジャーメーカーからも出てくるんだろうなあ。
ところで、CATVでこうしたルーターを使って複数機器を接続して良いか、否かだが、一般には禁止しているとこが多いようだ。うちのエリアの業者も、原則は2台までらしい。2台まではグローバルIPがDHCPで振られるようだ。3台以降は別途料金とのことだが、ルータでの接続については、どうも黙認しているようだ。このあたり、今は過渡期だから良いが、より一層普及してくると問題になりそう。
いずれにしても、近日中にはどれで行くか決めなければならない。ADSLをにらみつつ、取りあえずISDN常時接続を選ぶか、当面の本命との呼び声も高いCATVを選ぶか。悩ましいところだ。
<00-04-08>
VAIOで2000
VAIOにWindows2000をインストールしてみた。数週間前に仕事で使うので同じマシンにNT Serverを入れたのだが、その時はすごく苦労した。良く落ちるし、インストールもうまくいったりいかなかったり、謎の現象が続いた。しかし、2000の方はあっさりと言って良いくらいうまくいった。セットアップFDからの起動で、PCMCIAのSCSIカードも認識し、CD-ROMから問題なくインストールできた。
Petium133で1G HDDのマシンなので、2000を入れるのにはかなり厳しいのだが、思ったよりも快適な感じだ。ディスク容量はいかんともしがたいので、NTFSの圧縮ドライブ機能を使ってみた。空き容量が450MBくらいになったので、何とかいけそうだ。システム上は標準PCとしての認識だが、電源管理でAPMの項目の設定もできた。ハイバネーションもサポートしており、必要最小限の使用についてはOKだ。
し、しかし、今度はメインサーバーに不具合発生!
突然ブルースクリーンになってメモリダンプをはじめた。特に何をしたわけでもなく、NTバックアップを起動しようとスタートメニューを追っている最中に落ちた。直前には、VAIOへのソフトのインストールと、オフラインフォルダの生成くらいしかやってない。何で落ちるんだ? しかも、その後再起動もうまくできなくなってしまった。ログオンまではいくけど、デスクトップが出現する前に、同じようにブルースクリーンで落ちてしまう! 一体何が?
その後、一度はうまく起動したのだが、結局、10分も経たずに、操作中に突然落ちてしまった。しかも、その時の落ち方は、いきなり落ちるのではなく、"lsass.exeが落ちたので、30秒後にシステムをシャットダウンします"とかってアラートを出して落ちやがった。何だかすごく恐い。
うーん。ABITのACPIサポートのベータBIOSも出たことだし、再インストしようかな。でも、面倒だなあ。こんな致命的な落ち方で、2000Server大丈夫なのか?
<00-04-03>
Batch98で快適インストール
会社で、Batch98を使ったWindows98の無人インストールの話を聞き、試してみた。Batch98.exeは、Windows98 CDの中に添付されているのだが、インストール中に聞いてくる、CDキーや個人情報を予め入力して、INFファイルに書き出す機能がある。setup時に、
setup a:\msbatch.inf /pj
みたいに、INFファイルを指定してやれば、後は勝手にインストールしてくれる。これは超楽。昔問題になってた、起動ディスクの作成のところで止まる・・・という問題も、ASPI周りをAdpatecから落とした最新のものに変えたらうまくいくようになった。これで作業効率大幅アップ。
<00-04-01>
ACPI問題
AOPEN AX6BC PRO2の新しいBIOSがリリースされ、Win98/2000のACPIに対応したようだ。早速ダウンロードしてBIOSを更新する。DOS/Vマガジンを読んでて初めて知ったのだが、Windows98マシンをACPIでセットアップする場合は、
setup /pj
と、マニュアルでオプション指定してセットアップを実行しないといけないそうだ。やってみると、確かにちゃんとACPIマシンで構成され、電源の遮断もきちんとできる。デバイスマネージャを見ると、ACPIのコンポーネントが組み込まれているのが見て取れる。
Windows2000の方も、強制インストールとかしなくても、きちんとACPI状態でセットアップされるようになった。電源遮断も問題ない。HCLとインストールモードは無関係なのね。これは、ほっとした。
それから、金曜日にマイクロソフト主催のセミナーに出て判ったのだが、2000サーバーも、ACPIでセットアップすることができるらしい。うちの環境で、2000PROだとAPMになるマシンが、2000SERVERだと標準PCになってしまうと言う問題があったが、これは2000SERVERがACPIはサポートするが、APMはサポートしないことに起因しているようだ。APMの管理は16ビットコードのコンポーネントを使うので、2000SERVERで使うのには好ましくないそうだ。で、ACPIか標準PCかの二極になっているとの事。でも、それだと、2000PROにしても、APMだとあまり良くないということになるなあ・・。
現在、サーバーに使ってるABITのマザーの方は、いまだにACPI対応のBIOSがリリースされてないので、当面は標準PC状態で我慢するしかなさそうだ。ちなみに、サーバーにACPIを組み込むのは無意味かと言うと、そうでもないらしい。SOHOとかホームサーバーのような、使ってないときは省電力状態にしたいサーバーには最適だそうだ。Wake On LANなんかと組み合わせると、使うときだけ起動させることもできるそうだ。レスポンスは悪いそうだが、常時起動や、使うたびに起動よりはずっとスマートだ。うちのような、ホームサーバーにはぴったりだなあ。早くABITマザー、ACPIに対応しないだろうか?
いやあ、それにしても、このマイクロソフトのセミナーの講師は、やけに詳しい人だったなあ(MSの人ではないが)。技術的にも、オタク的にも、良く知ってる人だった。感心してしまった。
<00-03-29>
SB Liveのエラー
COPPERMINEにしてから、Windows98の起動直後に、エラーが出るようになった。はじめは、オーバークロックが原因かと思ったのだが、定格にしてもでるし、大体に、EMU101.VXDがなんたら・・という、サウンドブラスターまわりのエラーのようだ。何かドライバーが壊れたくさいので、再インストールしてみるが、一向に直らない。LiveWareを入れた時点からエラーが出る。で、困り果ててクリエイティブのサポートに電話したら、あっさりと、それは既知のエラー(有名らしい・・まあ、そりゃあそうだろう。)で、アップデータがWebに上がっていると言われた。いつも、LiveWareの方は見てたのだが、それとは別にドライバのアップデータが存在していた。履歴を見ると、COPPERMINEコアのCPUでの不具合を解消とあるが、CPUの製造プロセスの変更で、ソフトウェアが影響を受けることなんかあるのか? びっくりした。でも、まあ確かに、このドライバで問題は解決した。
ところで、COPPERMINEのオーバークロックの方だけど、色々テストしてみると、スーパーパイとかだと、500万回くらいまでは大丈夫だけど、1000万回だとエラーが出る。一般的な利用なら、100万回パスでも問題ないみたいだけど、ちょっと気にかかるところだ。ファンをアルファとかに変えたほうが良いのだろうか?
<00-03-25>
Intel Pentium !!! 600E \26,800@ソフトアイランド
SOLTEK SL-02A8++ \2,980@ソフトアイランド

しばらく河童を買おうかどうか、思い悩んでいたのだが、ふいとソフトアイランドに立ち寄ったら、26,800円と格安だったので、つい買ってしまった。FC-PGAで、FSB100MHzのやつ。下駄がいるので、SOLTEKのを一緒に買う。下駄って、結構相性あるらしい。SOLTEKのは評判良い。
当然、オーバークロック使用を目論んでの購入だが、ビデオカードがMGA-200のAGPなので、ここがボトルネックになりそう。駄目もとでFSB133の800MHzで動かしたら、意外にもあっさりOK。FANも標準のものだし、メモリも、モセルとかの特別のものではなく、先月買った現代のPC-100もの。でもCL2-2-2で動いてる。
CPUとしては、133以上でもいきそうだが、周辺がついていきそうもないし、これから暖かくなるので、この辺りで止めておくのが無難だろう。
<00-03-05>
Windows2000server顛末期
Windows2000のルータ勝手に発信現象がなかなか解決しない。DNSやDHCPのサービスまで止めてみたのだけど、直らない。しかたないので暫定処置としてルータのIPフィルタリング機能で2000serverからの接続を止めるようにしたが、どうにもきにくわない。原因付き止めたいよなあ。でも、一生懸命2000serverがルータに対して接続要求するのだけど、がんとしてはね付けられる様をアクセスランプで見てると(本当にそうかは判らないけど、パケットのランプがパカパカつくが、接続ランプはがんとして点灯しない様を見てると、そんな様が脳裏に浮かんでくる。)、ざまあみろ2000server、とちょびっとだけ痛快な気分になる。
その他の環境は、従来とほぼ同じレベルで使用できるようになる。バックアップも新しいNT backupに移行完了。スケジューラ機能が内蔵されたので、すごく楽になった。FTPも立ち上げ、Macファイルの自動バックアップも可能になった。ファイル共有も完了して、MacからでもWindowsからでも読み書きできる。プリンタもセットアップし、TCP/IP印字で問題なく出力できた。取り敢えず、一通りOKで落ち着いた。
<00-03-03>
Windows2000使用感
会社で1週間以上使ってみた。不可解なのは、休止モードにならないという現象。"プライマリIDEデバイスがだめよと言っている"と言われるのだが、何が原因かわからない。怪しそうなCDR書き込みソフトが入れたASPIマネージャを外してみたが、それでも同じだった。
それから、時々正常終了しないこともある。このマシンには、うっかり大昔のWinCDR(といっても3年くらい前)を一度入れてしまったので、何かゴミが残ってるのかもしれない。ちなみに、リムーバブル記憶域から見ると、CDRドライブに×がついている。書き込みとかは問題ないのだが、CDRドライブ周辺とシステムとの間で、何らかの不整合があるのかもしれない。でも、それ以外はおおむね良好。タスクバーをランチャー化させるのは便利だし、コントロールパネルの展開や、マウスポインタの自動追尾は、いずれも従来はレジストリをいじったり、別ソフトを入れなければ実現できなかった機能だが、標準装備されてるのは喜ばしい。Celeron433+128MBメモリ環境だが、非常に快適に動作している。ただ、困っているのが、会社のプリンタと接続できない点。会社のプリンタはXeroxの複合機(able)で、PRINTDIRECTという、独自プロトコルを利用してのネットワークダイレクト印字を行っているのだが、このPRINTDIRECTがWindows2000への対応予定がないらしい。Web見ると、Windows2000の場合はTCP/IP印刷サービスを使ってくれと書いてあるのだが、会社のableにはIPアドレスが割り振られてない。これが、実用的には一番困っている。
<00-03-02>
メーラをEudora4.2へ移行
Macのメーラを、Eudoraの4.0から4.2へ移行する。アップデート自体は問題なかったけど、4.2にしたら、急にキーチェーンが働くようになった。なんかキーチェーン絡むと、動作が遅くなるような気がするのだけど、錯覚だろうか?でも、キーチェーンの機能をdisableしようとしてもうまくいかない。機能拡張マネージャではずしても、初期設定ファイルを消してもダイアログが出てくる。それから、Eudora4.2自体もおもくなってるような気がする。起動するのに時間がかかるようになった。使い勝手は多少良くなったけどね。メール本文が受信ダイアログの中に、一覧と並んで表示されるようになったのはいい。ちょっとMacらしくないような気もするけど。
Pocket WZは快調
JornadaのPocket WZの方は至って快適。メーラは本当に出来いいなあ。速いし、見やすいし、使いやすい。これでけでも商品になるよ。Eudora CEは、返信文を書こうとすると途端に日本語入力が重くなると言う大きな問題があったしなあ。まあ、試用版だったから直っていると思うけどね。Editorのほうも、これまで使ってたEpisodeよりずっといいよ。これも、今Pocket WZで書いてるんだけどね。
<00-03-01>
Pocket WZ 2.0 \5,200 @ビックカメラ
今まで使ってたEudoraの試用版が期限切れになったので、メーラ+エディタの定番、Pocket WZを買う。素晴らしい。何で早く買わなかったんだろうか? Episodeとかっていう変なエディタをはじめに買ってしまったから躊躇してたんだけど、WZの方が全然良い。しかも、エディタだけでなく、メーラも良い。Eudora for CEより全然いいぞ。これはお買得だったが、何でもっと早く買わなかったのかと後悔の念が強い。
<00-02-27>
やっちまった、24時間接続
やられた。Windows2000に。DNSが勝手に5分おきに参照にいってた。土曜の夜から24時間、2000サーバを起動していた間、ほとんどつなぎっぱなし。まいったなあ。NTTにただで金をくれてやってしまった。これで、3回目かなあ。しかし、こちらに非があるとは言え、マイクロソフト製品にやられ、NTTに金くれてやったというのは、すごい腹立たしい。くそー、早く常時接続に切り替えたいぜ! きっと日本全国同様の目にあった人はたくさんいたはずだ。NTTぼろ儲け。
しかし、いまだにどこの設定いじれば解消できるか判らない。DNSの設定のとことか、怪しいところは全て直したけど、まだ発信するんだよなあ。困ったなあ。
<00-02-25>
Adaptec Toast 4.0J \9,800 @ベクターオンライン
やっと出た。Toast。アナウンスがあってから半年以上。何でこんなに遅れたんだか?
機能的には、ディスクアットワンスに対応したのと、俺的にはあまり関係ないけど80分メディアに対応したのが大きいのか。目立つとこだと、CD Spin Doctorとか、PhotoReadyとかが売りみたいだけど、まあ、実際にはあまり使いそうもないなあ。でも、あらためてToastのマニュアルに目を通したけど、一見すると単純そうなGUIの中に非常にたくさんの機能がつまってる。しかも、それらが全てバランスよく成り立っている。Adaptecは好きではないけど、Toastはいい。BHAやAplixもがんばってると思うけど、Mac用に関してはどうしてもToast以外使う気になれない。後はDirectCDを日本でも出してほしいもんだ。
<00-02-20>
案の定、WIndows2000で四苦八苦
都合3台のマシンにインストールする。しかし、まあ、案の定と言うか、苦しまされた。10回はインストールしたなあ。今回は3台とも新しいコンフィグレーションだったので、当然と言えば当然。いずれも些細な問題ではあったのだが。
はじめの障害は、ABITのマシン(サーバ)にのせたTop-GのCD-ROMからブートできないというもの。これはWin2kとは無関係。固体の不良なのか、こういうものなのか判らんが、Top-Gなんていうマイナーなメーカーなので諦め、さっさと別のマシンのミツミの24X CD-ROMと交換する。しかし、このTop-GのCD-ROMって、52Xなので、俺の環境の中で最速だったのだが、一瞬で退いてしまった。
で、CD-ROMを交換してからは順調で、ABITマザーにはWin2Kサーバ、AopenマザーにはWin2K PROをインストールしたが、特に問題はなく完了した。が、しかし、実際は問題があった。ACPIまわりだ。ABITの方は、全くACPIマシンとして認識されず、旧来の標準PCとして認識される。当然オートパワーオフはできない。休止(ハイバネーション)も無理。Aopenの方は、少しましで、APMマシンとしては認識されている。しかし、APM機能をオンにしても、やはりオートパワーオフができない。真っ黒い画面で終わる。ここからがまずかった。原因が判らないので、マザーのBIOS変えたりとかはじめてしまったのだ。泥沼。途中で、本やらWebやら見てたら、ACPIはインストールの最初で決められ、後で変更はできないと書かれている。中には強引に後から変更する方法も書かれてたが、最悪システムが起動しなくなる、との忠告通り、動かなくなってしまった。
で、最終的には、win2000j.comに書かれていた、インストールの頭でF5キーを押して、手動で環境を指定するという裏技を使った。これって凄くて、この時の手動指定メニューには、486PCとか、SGIマシンとか、色々な特種環境が並んでいた。このメニューの中に、ACPIがあるので、それを選んで強引にインストールするのだ。ACPIは、HCL上にない環境については、新しいマシンでも非ACPIとしてインストールするようだが、これじゃあ、これからの新しいマシンはどうすんだ?
ちなみに、以前、RC3で、Giga-Byteにインストできたのは、このGiga-ByteのGA6BXCがキチンとHCLに載ってたためだろう。インスト途中でBIOS上げろとかとも言ってきたし、HCLにあるものはきちんとサポートされてるようだ。ABIT BX6r2と、Aopen AX6BCPRO IIの二つは載ってなかった。くそー。
で、強制ACPIでどうなったかというと、一応問題なくインストでき、ACPIマシンとして動作するようにはなったのだが、やはりオートパワーオフがうまくいかない。ハイバネーションの時はうまくいくんだが。面倒なのでここで諦める事にする。

で、最後の一台は、Book PC。これは一番楽だった。これもやはりACPIにはならないんだけど、APMにはなって、しかもきちんと動作してくれた。しかし、この同じマシンに、W2Kサーバを入れたところ、これは非APMマシンになってしまう。もしかしたら、W2Kサーバでは、APMやACPIは働かないようにしてるのだろうか?確かにサーバで省電力管理というのもおかしいしなあ。ということで、ABITの方は強制ACPIインストールはせずに、標準PC状態で諦める事にした。
これで終わりかと言うと、当然そうはいかず、結構変わってしまった管理機構に悩まされる。RC3で慣れてたつもりだったのだが、サーバ版は設定項目も多い。GUIを結構共通化してるのだが、それが結構判りづらかったりもする。また、PDCとしてセットアップすると、ActiveDirectoryが組み込まれ、DNSとかDHCPもインストされる。で、当然このDNSがエラーを出したりするのだが、どうすりゃいいのか良く判らん。結局、最低限のセットアップを終えたところで疲れて中断したが、しばらくいじらにゃ判らんな。さすがに難しいや。
<00-02-18>
Windows2000 Developer優待アップグレード版 \68,800 @ ビックカメラ
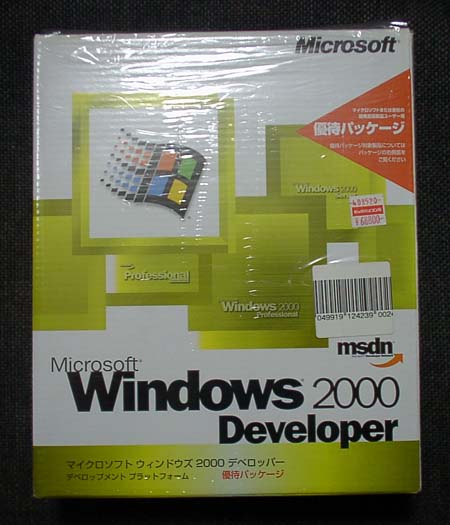
発売日当日の午前中、ビックで買う。ヨドバシは混んでたけど、ビックは空いてた。ビックは高いような気がしたのだが、ヨドバシは同じ商品が74,800円だから、まだマシだった。予約特典でWindows2000スタートアップガイドという日経BPの本をもらった。
中身は、Win2000 PROとServerのCDが2枚と、あとMSDNのCDが4枚くらい。シリアルはジャケットに印刷されてるから、もしかしたらDev版のはパッケージは全て共通なのかもしれない。ちょっと嫌な感じだ。ちょっと高いけど、まあこんなもんかなあ。
<00-02-16>
ABIT BX6 2.0 \8,980 @ ソフマップシカゴ館

うーん、結局マザー買ってしまった。GIGABYTEのGA6BXCがどうしてもうまくいかないので。で、何にしようかかなり悩んだんだけど、ABITのBX6 2.0リセール品(返品ものを再出荷したもの)が安かったので、これにした。はじめは、BXマザーをまた買うのが嫌だし、安いので、Apollo PRO133のABITかGIGABYTEのにしようかと思ったのだけど、ApolloとWindows2000の組み合わせが大丈夫なのか今一つ不安だったので、結局BXに落ち着いてしまった。もうこれ以上ハマりたくないからなあ。で、マザー入れ替えたところ、全く問題なくブートするようになった。まあ、当然だが。しかし、スッキリしたああ!
しかし、ABITって今一つ不安なところもあるので、キチンとインストして使ってみないと安心はできない。それにしても、GIGABYTEのGA6BXCは酷かったなあ。今にして思えば、よくあんなマザーを1年半も使ってたよなあ。
で、とにかくこれで、Windows2000発売前にして、3台のPCが口を開けてスタンバイの状態になった。今週末は忙しそう。
<00-02-16>
一年ぶりにEXPOで生ジョブス
ついでに購入 EUDORA4.2J \4,980 @EXPO秋葉館
一年ぶりにMac EXPOで生ジョブスを見る。去年と同じように長蛇の列だったけど、あっさり皆会場に入れて座れてた。
今回は、予想外に新製品発表が多く(インパクトの強いものものは少なかったが)、かつ、日本ならでは発表もありなかなか楽しめた。OSXやiMovieのデモも、話には聞いていたが、実際見るとより良いなあ。iMovie簡単で良さそうだけど、なかなかDV編集ってやらないよなあ。でもいいなあ。
OSXはやはり格好いい。ジョブスのデモ見てるとすっかり洗脳される。でも、個人的には、新しいFinderや、有機的な動作も実際に使うとどうだろうか?と多少の疑問も残る。まあ、こればっかりは使ってみないとなあ。
あと、興味引かれたのは、大日本スクリーンのフォントがOSXに搭載されることかなあ。やっとモリサワの呪縛から解放されるのか?スクリーンはフォントベンダーじゃあないから、フォントで稼ぐより、自社のフォントがDTPのメインストリームにのってメジャーになることの方がメリット多そうだからなあ。モリサワの次の一手が気になるし、そろそろ写研とかも動くんじゃあないか?
新製品では、New PowerBookがバランス良さそうで欲しいけど、まあ我慢できるかなあ。今年はOSXが出る夏以降、早ければ秋にメインマシン買い換えになるかもしれない。それまではお預けだな。
蛇足だけど、会場の即売でEUDORAを買う。まあ、安かったので。クロスライセンスだったし。
<00-02-11>
AOpen AX6BC PRO II \15,800
現代 PC100 128 CL2 DIMM \14,500
Quantum FBLCT 1.3G (5400RPM/ATA66) \12,800
@TWOTOP

Windows 2000特需で、PCパーツをもろもろ買う。メモリとHDDは、組み立て中のBook PC用に。廃品利用する予定だったのだが、欲が出てきて、全部買いそろえてしまった。結局Book PCには、60000円以上の投資をしてしまった。何だかなあ。しかも、俺が買った直後あたりから、メモリが暴落。すでに日曜の時点の最安値は12000円で、3月まで下がり続け、また10000円割れを起こすのではないかとの事。今回は定評ある現代のものにしたが、どうも最近のクロッカアッパー達の情報によると、モセルバイタリックとかがすごく耐性強いらしい。FSB170とかいくらしい。信じられん。しかし、モセルって、どこのメーカーなんだ? 聞いた事ないぞ。最近、神和とかもモセル多いよね。
一方のマザーは、メインマシンにのせ、代わりに従来のGIGABYTEマザーをサーバーにのせ変え、遊んでいたCELERONを載せる。本当は、メインマシンのCPUも、Pen3の600Eあたりにしたかったのだけど、ものが少なく、値も張るので今回は断念。でも、せっかくクロックアップ耐性が強く、BXの最終形と言われる、AX6BCPRO2を買ったのだから、CPUも変えたいなあ。
しかし、まいったのは、従来のGIGABYTEマザー。これをサーバーマシンの方に載せたら、全然電源が立ち上がらない(というか、すぐ落ちる)。もともとこのマザーは同様のトラブルで悩まされ、電源変えたりなんやらで、何とか使ってきたものだった。それでも、ここしばらくは好調で、問題もなかったのだが、換装したとたんに問題爆発だ。しかし、このマザーは前から、CPU変えたり構成変える度に問題を露呈した。しかも、何が原因かさっぱり判らない。今回も、ボードの位置を変えたり、CPUを抜き差ししたりで色々やったのだが、ちっとも良くならない。もうちょっとうんざりしてきたので、買い替えようかとも思ってるのだが、なんかこの時期にBXマザーをニ枚も買うのやだなあ。何とかならんかなあ?
<00-01-29>
Adobe GoLive 4.0J MAC
\17,800@ビックカメラ
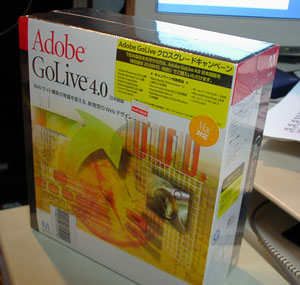
Adobe GoLiveのクロスアプグレード版を買う。Macromedia Dreamweaverもキャンペーンで安いので迷ったのだが、これまでの人生でマクロメディア製品をまともに使えるようになった覚えがないので、GoLiveにした。DirectorもFreeHandも高い金出したけど宝の持ち腐れだったもんなあ。
まあ、でもGoLiveもAdobeと言っても買収されたものだから、まだアドビ色強くないよね。しかし、今後PhotoshopやInDesignなどとの連係も考えられるので、一社にまとめておいた方が無難だろう。GoLive自体、以前のCyberStudioの時代から、Dreamweverより評判良かったしね。
それから余談だが、Windows2000 Dev版の予約をしてしまった。うーん、高いけど、当分使えそうだし買うならこのタイミングしかないだろう。Webでのシリアル登録とかアップグレードが恒久化かしつつあるので、これからはやはりきちんと正規ユーザーになってないとまずいしね。
<00-01-20>
Logicool First Mouse
\1.780@PC夢工房
一年前にも同じ店で、ロジクールのマウス買ったなあ。今回はPS/2仕様のもの。Book PC用に買う。しかし、安いなあ。
<00-01-09>
Intel Celeron 433
\7,980@パソコン工房3号店

ベアボン用に結局Celeronを買ってしまう。実は買おうかどうしようか悩んでたのだが、探したら500より低いCeleronって、ほとんどもう在庫限りで置いてある店が少ない。そうなると余計に物欲が湧いてくる。433のCeleronは、8000円以上の店なら結構あったのだが、しゃくに触るので何とか7000円台を探そうと歩きパソコン工房で7980円で売ってたのでゲット。まあ、リテールボックスなのでサンヨー製のファンもついてるし、CP比は高いのかもしれない。
このCPUを使い、ベアボンの動作チェックをしたが、問題はなし。64MBのメモリと4GBのHDDは余ってるので、既にもう組み立てることはできるのだが、最終的にWindows2000にするので、仕上げるのは少し待つことにする。しかし、このマシン驚いたのは、ブートデバイスがないとROMの中のNetwareクライアントソフトが立ち上がるようになってる。それから、BIOSでFSBとかいじれるようになってるし。よく出来てるなあ。
<00-01-05>
BOOK PCベアボンキット
\21,800@PC Next
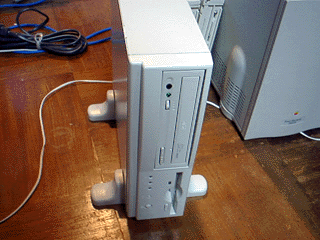
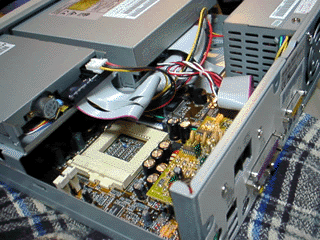
年末から気になっていたi810ベースのベアボンキットを結局買ってしまう。
これは結構いいなあ。基本スペックは...
i810マザーボード(Socket370、DIMMx2スロット)
オンボードVGA with 4MB VRAM
オンボードサウンド
10/100Base LAN
モデム
52x ATAPI CD-ROM
FDD
S-Videoアウト
スリムケース
といったところ。
しかも、付属のCD-ROMにはMP3エンコーダやWordPerfect8(英語版)なんかもついてる。Windows2000用のドライバも収録されてる。
しかし、残念だった点がいくつか。
まず、付属のCD-ROMが、店頭品はミツミだったのに、買ったやつはTop-Gloryとかいう聞いたこともないメーカー品だったこと。
マニュアルに記載されてるWinDVDがオプションでCDには収録されてなかったこと(このBook PCには、いくつかのバリエーションがあり、フェイスとかで売られているキーボード、マウス付きの25,700円のものにはついていたようだ)。
それからこのPCは会社でJornadaの母艦として使用しようと思ってたのだが、シリアルポートがなく、同期がとれない点。
こんなところか。
でも、とにかくCP比高く満足度も高い。デザインもいいし。
あとは、このマシンに付けるCPUやメモリをどうするか。
なるべく金かけたくないんだよなあ。
|